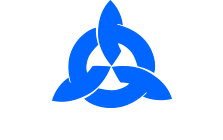平成22年度広報誌掲載分
- [2016年5月6日]
- ID:69
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

広報1月号掲載分
みなさん、こんにちは。寒さがきびしい季節になりました。
今回は、小学校・ふれあいセンター・児童館などで行って いる『放課後児童クラブ』をご紹介します。
放課後児童クラブとは、「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童でその保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」を対象としております。各クラブでは児童の健全育成を目的とし、年間計画にそって、毎月の誕生会・避難訓練・四季を通しての催しなどを行い、放課後児童指導員のもと異学年の児童がかかわって生活を送っています。学校によっては年間を通して4~6年生まで利用しており、夏休みのみ4年生以上の児童が利用しているクラブもあります。また、平成22年度から舟島・第一小学校区放課後児童クラブと子ども教室が一緒に活動する子どもプランが始まりました。
阿見小学校区放課後児童クラブ(学校区児童館)
室内で遊ぶほか、館庭ではドッジボールやサッカーなどで遊んでいます。また、隣接している児童公園で自然物や昆虫などとかかわった遊びを楽しんでいます。
本郷小学校区放課後児童クラブ(二区児童館)
室内では囲碁・将棋・工作などで遊んでいます。屋外では中庭を利用して一輪車や縄跳びなどで遊んでいます。
第一小学校区放課後児童クラブ(第一小学校専用施設)
紙芝居・読み聞かせ・将棋・ブロック・ままごと・ゲーム・クイズなど創意工夫した遊びや、校庭で思い切り体を使って遊んでいます。
舟島小学校区放課後児童クラブ(舟島ふれあいセンター会議室)
室内ではオセロ・将棋・折り紙・フラフープ・竹馬などで遊んでいます。戸外ではサッカー・野球・バドミントン・鬼ごっこなどの集団活動を中心に児童のかかわりをはぐくんでいます。
第二小学校区放課後児童クラブ(第二小学校の空き教室)
教室内のほか、広い校庭のアスレチックや固定遊具でのびのびと遊び、異学年の子どもたちと仲良くかかわりながら過ごしています。
実穀小学校区放課後児童クラブ(実穀小学校の2階空き教室)
1年生から5年生まで利用しており、異学年のかかわりがお互いの信頼関係を築き家庭的な雰囲気で集団遊びを楽しんでいます。
君原小学校区放課後児童クラブ(君原小学校図工室)
室内では将棋やごっこ遊びなど異学年の児童が一緒に遊んでいます。校庭ではサッカー・ドッジボール・鬼ごっこなど約束ごとを守って仲良く遊んでいます。
吉原小学校区放課後児童クラブ(吉原小学校理科室)
児童の人数も少ないので指導員と一緒に絵本や紙芝居を読みあうなど家庭的な雰囲気のクラブです。




広報12月号掲載分
こんにちは。町には、学校区児童館(阿見中学校プール隣)と二区児童館(二区保育所隣)の2館があります。児童館は、乳幼児とその保護者・小中高生が自由に利用できるところです。詳しい活動内容については、各児童館に問い合わせてください。
(お問い合わせ) ▼学校区児童館 029-887-4093▼二区児童館 029-843-3282
児童館でやっていることを教えてください

乳幼児とその保護者を対象として、『育児サークル』を行っています。育児サークルは、子育て支援センターとも連携して活動を進めています。活動の内容は、絵本の読み聞かせ・手あそび・リズムうんどう・作ってあそぼう・親子の触れ合いあそびなどです。
また、多くの人に児童館での活動を知ってもらえるように『うごく児童館』として町内の公民館や公園に出向き、パネルシアター・バルーンアート・音楽会・運動会などの活動を年に数回行っています。民生委員児童委員や更生保護女性の会の人たちにも活動をサポートしていただいています。
小学生対象のお楽しみ会などありますか?

小学生を対象とした、一輪車・押し花・ダンス・バドミントンなどのクラブ活動を行っています。毎年『まい・あみ・まつり』のキッズ・パフォーマンスに参加しており、今年は学校区児童館が一輪車クラブで、二区児童館はダンスクラブが出場しました。
季節ごとの行事としては、レッツパーティーやおもちつき会、また地域の人たちと触れ合う地域交流会として、囲碁・将棋・竹馬・お手玉・あやとりなどの伝承遊びを計画しています。
参加者については、そのつど募集をしていますので、お友達を誘って遊びに来てください。
母親クラブは、どのようなことをしているグループですか?

母親クラブは、阿見町に在住している母親が中心になって活動しているグループです。
どんぐりクラブ(学校区児童館)とさくらんぼクラブ(二区児童館)の2クラブがります。
活動を通して、子育てや健全育成について学び合いながら、地域の活動などにも積極的に参加しています。
○どんぐりクラブ
(ミュージックベル・バドミントン・テニス・コーラス・手芸・季節のイベントなど)
○さくらんぼクラブ
(人形劇・エプロンシアター・フラ ワーアレンジメント・オーナメント作り・親子のふれ あい遊び・季節のイベントなど)
広報10月号掲載分
みなさん、こんにちは。澄んだ空の下、元気に飛ぶ赤とんぼの姿が秋を感じさせる季節となりました。
今回は、『2~ 3歳児の遊び』に関するQ&Aです。
身近な物を使った遊びは、どういうものがありますか?

家庭にある身近な物を使った簡単な遊びとして、布遊び(ハンカチ・風呂敷など)があります。布は、顔を隠して「いないいないばあ」やバックにして物を入れたり、体に巻いてのごっこ遊びも子どもは大好きです。空き箱を使って乗り物ごっこをしても楽しく遊べますね。
子どもと一緒に体を動かす遊びには、どういうものがありますか?

子どもは、身近な大人と一緒に体を使って遊ぶことが大好きです。大人のひざの上に子どもを乗せて「♪バスに乗って揺られてる ゴーゴー」と一緒に遊ぶのも楽しいですね。身近な大人と向かい合って「だるまさん だるまさん にらめっこしましょ…」とお互いの顔を見つめ合ってにらめっこ遊びも楽しめます。
同じ絵本を見るのが好きです。ほかの絵本を見せた方がいいのですか?

子どもは、表現がおもしろいものや、リズミカルな言葉のくりかえしのある絵本が好きです。読んでもらった絵本の中から、好きな絵本や気に入った絵本をみつけて何度も「読んで」と言います。好みの絵本を大人に、くりかえし読んでもらうことで子どもは絵本の世界に引き込まれ、夢中になります。心ゆくまで大好きな絵本を読んでもらった子どもたちは、感性や想像力が豊かに育っていくでしょう。
ブロックを使った遊びはありますか?

子どもは、身の回りにある物や、おもちゃを何かに見立てて遊ぶことが好きです。ブロックや積み木をつなげたり、積んだりするほかに「モグモグ」と言って食べるまねをしたり、耳にあてて電話しているまねをしたりと、子どもは、普段の大人の姿を見てまねて遊びます。
広報9月号掲載分
みなさん、こんにちは。まだ暑い日もありますが、夜になると虫の声もきこえるようになり、少しずつ秋の訪れを感じるようになりました。今回は、『2・3歳の生活について』に関するQ&Aです。
歯みがきを嫌がるので困っています

2~3歳の年齢では、乳歯もほとんどの子どもが生えそろい、いろいろな種類の食べ物も食べるようになってきます。そして、口の中をきれいにしたり、虫歯のない健康な歯のためにも欠かせないのが歯みがきですね。
このころの年齢では、まだ自分できれいにみがくことは、なかなかできないと思いますが、自分で歯をみがくという習慣を身につけることは大切です。
歯みがきを嫌がるお子さんに対しては、大人が歯をみがく様子を見せたり、鏡の前でみがかせたりするとよいでしょう。その時に「○○ちゃん、じょうずだね。」「虫歯さんもいなくなっちゃうね。」「きれいな歯だね。」などの言葉をかけたりしながら楽しくみがけるといいですね。
仕上げみがきでは、大人が力を入れすぎたり、強くこすりすぎたりしないことが大切ですね。あとは、買い物に行った時にお子さんと一緒に歯ブラシ選びをすることによって、歯みがきに関心が持てるようになるかもしれませんね。
外で人に会ってもあいさつをしません。どうしたらできるようになるでしょうか?

このころの年齢では、あまり会ったことのない人にあいさつすることは、はずかしがったり、戸惑ったりすることが多いかもしれませんね。
あいさつができないからといって「きちんとあいさつしなさい!」「どうしてできないの?」と頭ごなしに言われると、子どもは、あいさつをすることが嫌いになってしまうかもしれません。
あいさつの中には、目が覚めたら「おはよう」、食事の前には「いただきます」、食べ終わったら「ごちそうさま」などいろいろあります。
まずは、おうちの中で上手にできたことをほめるようにしてみるとよいでしょう。そうするとお子さんもあいさつの心地よさが少しずつわかり、自然とあいさつができるようになるでしょう。
「子どもは、親の後ろ姿をみて育つ」とよく言われますね。おうちの人があいさつをしている姿をみて、きっとお子さんもできるようになるでしょう。焦らずに見守っていけるといいですね。
広報誌8月号掲載分
みなさん、こんにちは。暑い日が続いていますが、日焼けした子どもたちは元気いっぱい。暑さに負けず、水遊びや虫さがしなどを楽しんでいます。今回は、『0~ 1歳児の遊び』に関するQ&Aです。
夏場も外遊びをしたいのですが、何か注意点はありますか?

子どもは外遊びが大好きです。暑い季節も工夫して楽しみたいですね。できるだけ日陰のある場所で遊び、直射日光に長時間当たらないように気をつけましょう。帽子をかぶり、散歩コースも木陰の多い道を選びましょう。アスファルトは熱を反射し、ベビーカー近くの気温は高くなっているので注意が必要です。外出時間を考慮し、出掛ける時には、水分をこまめにとれるようにしましょう。
手に取ったものは、何でも口に入れてしまいます。どうしたらよいでしょうか?

口に入れては危険なもの(飲み込んでしまう大きさの物・コイン・タバコ・電池等)は、お子さんの手の届かない場所に置きましょう。オモチャは壊れていないか確認し、水で洗うなどして清潔を心掛けるといいですね。口に入れてはいけないものを根気よく伝えていくうちに、何でも口に入れることはなくなります。子どもが安心して過ごせる環境をつくっていきましょう。
なにをしても泣き止まないことがあります。どうやってあやしたらよいでしょう?

心当たりのあることから一つ一つ試してみましょう。おなかはすいていないか、オムツは汚れていないか、暑すぎてはいないか…。病気でないときは、気分転換に外にでてみたり、音楽をかけてみたりするのもよいです。それでも泣き止まないときは、深呼吸して大人も落ち着きましょう。泣くのは小さな子どもの仕事だと思い、温かく受け入れられるといいですね。
一つの遊びにすぐ飽きてしまいます。このままでよいでしょうか?

一つの遊びが長時間続かないことは、小さな子どもの特徴ともいえます。集中力がないわけではなく、興味があるものへ次々と手が伸びていくのでそのように見えるのかと思います。子どもの気持ちを受け止め、お家の人も一緒に遊びを楽しんでみてはいかがでしょうか。
広報7月号掲載分
こんにちは。梅雨の晴れ間の青空が少しずつ広がるようになり、夏がすぐそこまで来ているようですね。
今回の子育てシリーズは、0・1・2歳児の生活についての子育てポイントをQ&Aのかたちでお送りいたします。
好き嫌いが多く、どのように食事を進めればよいかわかりません

1歳~2歳ころは食べることへの興味も出てくると同時に味覚も発達してくるので少しずつ好き嫌いも出始めてくるころです。
なるべくいろいろな味に慣れて何でも食べられるようになってほしいと思いますね。しかし、無理に食べさせようと時間をかけてしまうと、食べる意欲や喜びを損ないかねません。「これはどんな味がするのかな?」などと声をかけたりしながら、興味をもたせていけるとよいですね。
親子で体を動かす遊びを楽しんだり、食事の間隔を開けたりするなどおなかのすいた状態で食事の時間を迎えるなど、楽しい雰囲気で食事をすることも食べる意欲につながっていくと思います。
なかなかおむつがとれません。トイレトレーニングはどのように進めればよいですか?

トイレトレーニングには個人差があり、また排せつの間隔がどれくらいあいているかによっても違います。タイミングをはかりながら、起床時や睡眠前、入浴前などに無理なく誘い、興味を向けてみてはいかがでしょうか。
また、自我も芽生え反抗期の時期でもあり、何を言ってもだめな時もあります。嫌がらずにトイレに行き排せつに成功した時には、たくさん褒めて意欲が持続できるようにしていけるとよいですね。
トイレトレーニングは、行きつ戻りつの繰り返しです。夏におむつがとれたのに、冬になるとまたおむつが必要になることもあります。気長に焦らずゆったりとした気持ちで接し、進めていけるとよいですね。
夜泣きがひどく、度々大泣きをします。ぐっすり寝かしつけるにはどうしたらよいですか?

日中、よく遊んでみたり、散歩などに出かけたりして体を動かしてみてはいかがでしょうか。「犬がいるね。」「風が気持ちいいね。」と大人が見たもの感じたままを言葉で伝え、語りかけることで程よい刺激となり眠りに誘うことができるかもしれません。
また、入浴は寝る前、リラックス効果が得られるぬるめのお湯がいいようです。おむつ交換をしたり、お茶を飲んだり、明かりを暗くして心地よい眠りを誘うよう工夫してみてはいかかでしょう。
夜泣きはずっと続くものではなく、時期がくれば自然になくなっていくものです。これも成長の一過程と考え、気持ちを楽に持って受け止めていくとよいでしょう。