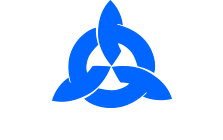固定資産税・都市計画税
- [2020年10月26日]
- ID:85
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産税・都市計画税について
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)の保有と市町村の行政サービスとの間にある受益関係に着目し、資産価値に応じてその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。
都市計画税は、道路・公園・下水道整備などの都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるための目的税として課税され、固定資産税とあわせて納めていただく税金です。阿見町では、都市計画法による市街化区域内および市街化調整区域のうち都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律による改正前都市計画法に基づく都市計画事業が施行された地域(南平台)内の土地・家屋の所有者に対して課税されます。
課税対象となる固定資産
| 土地 | 宅地、田、畑、山林、原野、雑種地など |
|---|---|
| 家屋 | 居宅、店舗、事務所、倉庫、工場など |
| 償却資産 | 土地・家屋以外の事業の用に供することができる資産 |
納税義務者
原則として賦課期日(毎年1月1日)現在の固定資産の所有者です。
| 土地 | 登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
|---|---|
| 家屋 | 登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
| 償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
税額の算出
(1)固定資産を評価して、価格を決定し、その価格を基に課税標準額を算出します。
(2)課税標準額に税率を乗じ、税額を算出します。
- 固定資産税の税額=固定資産税課税標準額×税率1.4%
- 都市計画税の税額=都市計画税課税標準額×税率0.3%
- 免税点(税金のかからない限度額)の制度
同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が下記の金額に満たない場合、固定資産税は課税されません。また、固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
| 土地 | 30万円 |
|---|---|
| 家屋 | 20万円 |
| 償却資産 | 150万円 |
納期
| 納期 | 納期限 |
|---|---|
| 第1期 | 4月30日 |
| 第2期 | 7月31日 |
| 第3期 | 12月25日 |
| 第4期 | 翌年2月末日 |
※納税通知書(納付書)は、毎年4月中旬、納税義務者の人にお送りします。
※都市計画税を課税している区域の場合は、都市計画税もあわせて納めていただくことになります。
※税額が3,900円以下の場合は、第1期のみとなります。
※各納期の納付額の平準化を図るため、平成26年度より端数処理の方法について1,000円未満を100円未満としています。
※納期限が土曜日、日曜日、祝日および振替休日に当たる場合は、その翌日が納期限となります。なお、12月25日が土曜日、日曜日の場合は、翌年1月4日以降の平日が納期限となります。
※納付には、便利で納め忘れの心配がない口座振替をお勧めいたします。
※コンビニでの納付もご利用いただけます。ただし、納付書1枚あたりの税額が30万円を超える場合(バーコードの印字なし)や納期限を過ぎた場合、コンビニでは納付することができませんのでご注意ください 。
固定資産の評価と価格の決定
固定資産(土地・家屋・償却資産)の評価は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づいて行い、町長がその価格(評価額)を決定し、この価格をもとに課税標準額を算出します。 土地と家屋については、原則として、3年ごとの基準年度に評価替えを行い、基準年度の価格を3年間据え置きます。
ただし、基準年度以外において、新たに固定資産税の課税対象となった土地や家屋、土地の地目の変換、家屋の改築等によって基準年度価格によることが適当でない土地または家屋については、新たに評価を行い、価格を決定します。
なお、土地の価格については、基準年度の価格を3年間据え置くことが原則ですが、地価の下落があった土地について価格を据え置くことが適当でないときは、基準年度以外の年度において特例措置による価格の下落修正を行うことがあります。
償却資産については、所有者からの毎年1月1日現在の償却資産の状況の申告に基づいて毎年評価し、その価格を決定します。
課税標準額
原則として評価によって算定された価格が課税標準額となります。ただし、住宅用地となっている宅地の課税標準の特例措置の適用や税負担の調整措置が適用される場合、課税標準額は価格より低く算定されます。
課税標準の特例
住宅用地に対する課税標準の特例(固定資産税・都市計画税)
居住用の住宅の敷地(住宅用地)については、その税負担を軽減するために、その面積の広さ等によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて課税標準の特例措置が設けられています。ただし、住宅用地には、家屋の床面積の10倍までなどの制限があります
| 住宅用地の区分 | 特例措置となる面積 | 固定資産税の特例 | 都市計画税の特例 |
|---|---|---|---|
| 小規模住宅用地 | 住宅用地のうち200平方メートル以下(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまで)の部分 | 価格の6分の1 | 価格の3分の1 |
| 一般住宅用地 | 住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分 | 価格の3分の1 | 価格の3分の2 |
宅地等の税負担の調整措置(固定資産税・都市計画税)
平成8年度までの税負担は、価格の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えから、課税の公平を観点に、地域や土地によりばらつきのある価格に対する前年度課税標準額の割合(負担水準)を均衡化させることを重視した税負担の調整措置が講じられています。
負担水準:個々の宅地の課税標準額が評価額に対してどの程度まで達しているかを示す指標で、次の算式によって求められます。
負担水準=前年度課税標準額÷(価格(評価額)×住宅用地特例率(※))×100
(※)固定資産税は6分の1または3分の1、都市計画税は3分の1または3分の2
| 負担水準の割合 | 課税標準額(固定資産税・都市計画税) |
|---|---|
| 70%超 | 価格(評価額)の70% |
| 60%以上70%以下 | 前年度課税標準額を据え置き |
| 60%未満 | 前年度課税標準額+価格(評価額)×5% ただし、上記算式で求めた額が、価格(評価額)の60%を上回る場合には60%相当額、20%を下回る場合には20%相当額となります。 |
| 負担水準の割合 | 課税標準額(固定資産税・都市計画税) |
|---|---|
| 100%超 | (1):価格(評価額)×住宅用地特例率(固定資産税は6分の1または3分の1、都市計画税は3分の1または3分の2) |
| 100%未満 | (2):前年度課税標準額 +(1)の額×5% ただし、上記算式で求めた額が、(1)の額を上回る場合には(1)の額とし、20%を下回る場合には20%相当額となります。 |
固定資産税関係申告書等ダウンロード
よくある質問
相続登記
登記簿に登記されている固定資産の所有者が亡くなっているとき、所有者を変更するためには、相続登記が必要となります。