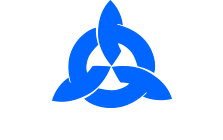災害時のデマに注意
- [初版公開日:2024年12月20日]
- [更新日:2024年12月20日]
- ID:14144
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
災害時のデマ(偽・誤情報)に注意しましょう!
大きな事故や地震などの災害が発生すると、インターネット上ではメールやSNS等で被災状況や被災者支援等のさまざまな情報が大量に飛び交うようになります。
SNS等は、災害時の情報入手や安否確認の手段としても役立ちます。
しかし、デマ(偽・誤情報)が拡散すると、多くの人の不安をあおり、救援活動にも支障をきたすなど、思わぬ弊害(二次被害)に繋がる恐れがあります。災害は一刻を争う緊急事態のため、人々の警戒心が弱まる傾向があり、このようなデマは被災された方々や人命救助を含む災害支援や情報伝達に悪影響を及ぼす原因となります。
このような誤った情報に騙されないようにご注意ください。
過去の災害時にあった事例
〇能登半島地震では、SNSを通じて「外国人窃盗団が能登半島に集結している」「息子がタンスの下敷きになって動けない」という悪質な虚偽の情報が発信され、警察が実際に出動するといった事態が発生し、被災地で混乱をもたらしました。
〇その他のデマとして、以下のようなものが考えられます。
「過去の災害画像を転用して被害状況を伝える投稿」
「存在しない住所と共に救助を求める投稿」
「二次元コード(QRコード)を添付して寄付金を求める投稿」
「支援物資や義援金を募るEメールやショートメール」
〇不確かな情報は安易に拡散せず、また二次元コード(QRコード)の読み取りをしないようにしましょう。
デマ(偽・誤情報)に騙されないためのチェックポイント
1 投稿された画像は本物か?過去の災害など、今回の災害とは無関係なものではないか?
2 信頼できる提供元からの情報か?(他のメディアでも報じられているなど)
3 支援を求めているアカウントは、実在する団体等ものか?
4 文字や文章の一部がおかしかったり、送信元のメールアドレスが海外のドメインであるといった不審な点はないか?
阿見町からの防災情報の主な入手方法
安心・安全なインターネット利用ガイド(外部リンク)