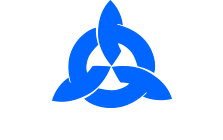食品ロスを減らそう
- [初版公開日:2024年03月07日]
- [更新日:2024年3月7日]
- ID:9694
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
食品ロスについて
食品ロスとは,本来食べられるにも関わらず捨てられている食品のことです。
日本国内では,年間約523万t(令和2年度推計量)の食品ロスが発生しています。
これを国民1 人あたりに換算すると、1日約114g(お茶碗1 杯分のご飯の量)の食品ロスが発生していることになります。
この523万tのうち,約53%(276万t)が事業系食品ロス(外食産業や食品製造・卸売業)で,約47%(247万t)が家庭系食品ロスとなっています。
食品ロスの問題は国際的にも関心を集めており,持続可能な開発目標(SDGs)のターゲットのひとつとして,食品ロスの削減が設定されています。
(参考:農林水産省「食品ロスとは」(別ウインドウで開く))
(参考:外務省「SDGsとは」(別ウインドウで開く))
家庭から出る食品ロス
食品ロスのうち約半分は家庭から出ています。
家庭から出た食品ロスは,買いすぎ,賞味消費期限切れ,過剰除去(野菜や果物の皮の厚剥き),食べ残しによって発生します。
食品ごみの行き先は
阿見町では,生ごみや食品ごみは焼却されており,その後は灰になって最終処分場に埋め立てられています。
家庭でできる取り組み
必要な分だけ買う
まとめ買いはできるだけ避け,必要なものを必要な分だけ買購入しましょう。
期限表示を確認する
賞味消費期限を確認し,すぐに食べるものは期限が近いものから購入しましょう。
また,冷蔵庫に保存してある食材も,定期的に賞味消費期限を確認しましょう。
料理で気を付ける
食べきれる分だけを料理しましょう。
また,食材の食べられる部分はできる限り無駄にしないようにしましょう。
自分でできることを知ろう
食品ロスの削減は、行政や食品関係事業者だけでは解決できない問題であり、消費者の協力も必要になります。
食品ロスの問題を知って、その削減のため、できることから始めていきましょう。
(参考:消費者庁「[食品ロス削減]食べもののムダをなくそうプロジェクト」(別ウインドウで開く))
(参考:環境省「食品ロスポータルサイト」(別ウインドウで開く))
阿見町食品ロス削減推進計画
食品ロスが増大すると、大量の食品が無駄になるだけでなく、可燃ごみとして運搬、焼却処分されることによる二酸化炭素(CO2)の排出及び焼却灰の埋め立て量の増加等の環境問題の悪化、ひいては地球温暖化の加速に繋がってしまいます。
国は令和元年5 月に「食品ロスの削減の推進に関する法律」を制定し、国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携した国民運動として食品ロスの削減を進めることとしています。
本町では、食品ロスの削減の推進に関する法律の趣旨を踏まえ、食品ロス削減に向けた取り組みを総合的かつ計画的に推進するため、「阿見町食品ロス削減推進計画」を策定しました。
阿見町食品ロス削減推進計画
フードバンク活動について
フードバンクとは,「食料銀行」を意味する社会福祉活動です。
まだ食べられるのに,さまざまな理由で処分されてしまう食品を,食べ物に困っている施設や人に届ける活動のことです。
阿見町役場、阿見町社会福祉協議会では,NPO法人フードバンク茨城と連携して,阿見町総合福祉会館(さわやかセンター)及び本郷ふれあいセンター内に「きずなBOX」(食品収集箱)を設置しています。
詳しくはこちらのリンクをご覧ください。