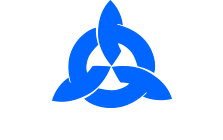阿見町名所百選 舟島小学校地区(その2)
- [2015年1月7日]
- ID:814
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
舟島小学校地区(その2)
桜の名所、舟島小学校を起点に丘陵地帯の名所旧跡を訪ねてみましょう。
霞ヶ浦にほど近いこのあたりでは、古代、付近に大規模な集落があったと考えられ、大昔の人々が食料とした貝の殻を今でも畑の中に見ることができます。
濃い緑影の中には、めじろやうぐいすなどの野鳥も多く、美しいさえずりを聞かせてくれます。
のどかな風景のなかに点在する名所をたどり、歴史に思いを馳せてみましょう。
舟島小学校地区 名所百選(その2)
37 吉田貞蔵碑 38 満徳寺 39 竹来の阿弥神社
※各項目に貼られている地図は、名所百選の看板の位置またはその付近を示しています。
※名所百選はわかりにくいところにあるものがあります。詳しくは生涯学習課へおたずねください。
37 吉田貞蔵碑
【上島津/名所百選No.37】
高さ2メートル63センチ、幅1メートルあまりのこの碑は、初代舟島村長吉田貞蔵を記念して建てられたものです。
吉田貞蔵は、明治22年(1889)6月に34歳の若さで初代舟島村長に就任した後、大正6年(1917)7月までの実に28年間を村政につくし、村の基礎を築いた人物です。
衛生、思想の普及、土木勧業、納税、貯蓄の勧奨に努め、特に学校教育の振興に意を注ぎ、舟島小学校の校舎建築に村民とともに献身的な努力を重ねました。
この地方自治の功績により、大正4年(1915)藍綬褒章(らんじゅほうしょう)を授与され、村の有志がその徳をたたえて彰徳碑を建立しました。
茨城県知事力石雄一郎の篆額、宮寺美成の撰文で、島津地区のJAいばらきかすみ前に建っています。
昭和20年(1945)6月10日の空襲により上部が欠けており、空襲のすさまじさを物語っています。
この碑の近くに湯原卜峩(ゆはらぼくが)の「磯山や沼にひかるる雉子の声」の句碑があります。
卜峩は島津村の名主で、本名は湯原惣右衛門といいます。江戸時代後期に阿見地域で活躍した俳人吉田麦翠(よしだばくすい)の句集『松苗集』や『俳諧画像集』にも各種の句が掲載されています。
38 満徳寺
日限地蔵尊
【掛馬/名所百選No.4】掛馬1268
掛馬山満徳寺は時宗の寺院で掛馬字東前にあり、本尊は阿弥陀如来(あみだにょらい)、本山は藤沢の清浄光寺です。
開寺は正和4年(1315)二祖真教の法弟の弥阿愍宣(みあびんせん)と伝えられています。
無住の時代に書類等を失い、古いことはわかりませんが、墓石から21世、22世、28世、32世等の住持の名と没年を知ることができます。
近年では、40世鈴木了善師、41世保科忍善師、42世小林了暁師が知られます。
小林師は大正12年頃来住し、地蔵を建立して以来、安産子育の「日限地蔵尊」として参詣人が続いています。
この宗派の特色は遊行上人による諸国遊行であり、町域の近世古文書にも、この遊行上人の来駕にともなう近在村方へ人夫割当の記事が見受けられます。
昭和に入っても3回の遊行があったといいわれており、「南無阿弥陀仏」と書いた小さな御札を手にのせてもらって往生の証とするものです。
当寺付近は中世に築かれた掛馬館と関連があると思われ、西側にある掛馬家の裏手の丘陵には、小規模ながら館の主郭部が残っています。
なお、丘陵のすそに宿と呼ばれる根小屋があり、平成4年にここの結束家の裏手から、渡来銭11万枚余が出土しました。
39 竹来の阿弥神社
宝篋印塔
【掛馬/名所百選No.9】
当社は、社伝によると祭神は武甕槌命(たけみかづちのみこと)で、御神体は円鏡です。
祭神については普都大神(ふつのおおかみ)とする説、豊城入彦命(とよきいりひこのみこと)とする説、高来(たかく)神とする説などもあります。
「常陸国風土記」に記された普都大神の説話が高来里のことであり、大神を祭る神社が竹来の阿弥神社であるとされます。
「延喜式神名帳」には、信太郡2座として楯縫(たてぬい)神社(美浦村)と阿弥神社が記載されていますが、この阿弥神社はどちらであるか、近世に竹来の阿弥神社と中郷の阿弥神社の間で論争が続きました。
竹来の阿弥神社は二の宮明神ともよばれ、「円密院文書」にも楯縫神社と共に「庄内第一の宋廟」と南北朝時代に称されていたことがわかりますが、式内社論争には触れないことにします。
本殿の立替えは、棟札によると元禄4年(1691)2月吉日であり、現在までの調査では、町域で最古の建造物です。境内にはその他に、拝殿、御神楽殿があります。神域を囲む杉の大木群は、天然記念物「阿見神社樹(じゅ)叢(そう)」として町指定文化財となっています。
なお境内には、吉田麦(ばく)翠(すい)の句碑「湖の風も通うて夏木立」があります。麦翠は竹来の人で、龍ヶ崎の杉野翠兄に学び、近世後期の町域農民に広く俳句を普及させました。
また、当社南方の竹来区公民館裏に、50基あまりの五輪塔(ごりんとう)、宝篋印塔(ほうきょういんとう)が安置されています。これらは竹来遺跡発掘調査の際、土中から1箇所で発見された南北朝以後の石塔です。