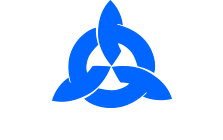施設サービスを利用した場合の居住費・食費の負担限度額
- [初版公開日:2022年07月07日]
- [更新日:2025年9月19日]
- ID:1678
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
施設サービスを利用した場合の居住費・食費の負担限度額
介護保険施設(ショートステイを含む)での居住費(滞在費)・食費は利用する人が全額負担することになっていますが、所得の低い人の負担が重くなりすぎないよう、利用者負担段階に応じて負担を軽減しています。(特定入所者介護サービス費等)
軽減を受けるには申請が必要です。有効期間は、8月から翌年7月までとなりますが、8月以外に申請する場合は申請日を含む月の初日からとなります。現在、軽減を受けている人が継続して軽減を受けるときは毎年申請が必要となります。(毎年6月中旬時点で軽減を受けている認定者の人には6月下旬に更新のご案内をお送りします。)
申請不要の場合
- 介護保険施設(ショートステイを含む)をご利用する予定がないとき
- グループホーム・有料老人ホームをご利用するとき
負担軽減の対象者について
負担軽減の対象者は、以下の表の『第1段階』~『第3段階』に該当する人です。
(第4段階に該当する人は対象外となります。)
申請をして対象となった人には『負担限度額認定証』を交付します。
令和7年8月から利用者負担段階の「80万円」が「80万9,000円」に変わります。
| 利用者負担段階 | 所得等の要件 |
|---|---|
| 第1段階 | ・本人および世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金を受けている人 ・生活保護を受けている人 |
| 第2段階 | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万9,000円以下の人 |
| 第3段階(1) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税・非課税年金収入額が80万9,000円超120万円以下の人 |
| 第3段階(2) | 本人および世帯全員が住民税非課税で、前年の合計所得金額+課税・非課税年金収入額が120万円超の人 |
| 第4段階 | ・本人が住民税を課税されている人 ・住民税が課税されている人が同一世帯内にいる人 |
利用者負担段階が、『第1段階』~『第3段階』に当てはまる人でも、(1)(2)のいずれかに該当する場合、『第4段階』となり、特定入所者介護サービス費等の給付の対象にはなりません。
(1)住民税非課税世帯でも、世帯分離している配偶者が住民税課税者である場合
(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者が住民税非課税)でも、預貯金等が一定額(以下の表「資産要件」)を超える場合
※配偶者が町外にいる方は非課税証明書の提出を求める場合がございます。
※虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還していただくことがあります。
| 利用者負担段階 | 資産額 |
|---|---|
| 第1段階 | 単身1,000万円、夫婦2,000万円を超える場合 |
| 第2段階 | 単身650万円、夫婦1,650万円を超える場合 |
| 第3段階(1) | 単身550万円、夫婦1,550万円を超える場合 |
| 第3段階(2) | 単身500万円、夫婦1,500万円を超える場合 |
| 第4段階 | 資産要件はありません。 |
居住費・食費の1日あたりの負担限度額
利用者は、居住費・食費を下表の負担限度額まで負担し、超えた分は介護保険から給付されます。
ユニット型 個室 | ユニット型 個室的 多床室 | 従来型 個室 | 多床室 | 施設サービス 食費 | 短期入所 サービス 食費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 880円 | 550円 | 550円 (380円) | 0円 | 300円 | 300円 |
| 第2段階 | 880円 | 550円 | 550円 (480円) | 430円 | 390円 | 600円 |
| 第3段階(1) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 650円 | 1,000円 |
| 第3段階(2) | 1,370円 | 1,370円 | 1,370円 (880円) | 430円 | 1,360円 | 1,300円 |
第4段階 | 2,066円 | 1,728円 | 1,728円 | 437円 | 1,445円 | 1,445円 |
居住費・食費の利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、基準となる額(基準費用額)が定められています。
上の表の第4段階の金額は基準費用額を記載しています。
※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額は、()内の金額となります。
※グループホームや有料老人ホームでのご利用はできません。
※通所系サービスの食費は対象外です。
窓口での申請に必要なもの
● 介護保険負担限度額認定申請書
● 同意書
● 対象者本人及び配偶者の通帳等の資産額がわかるものの写し
- 通帳の表紙(口座名義人と口座番号が確認できるページ)
- 定期預金のページ(定期預金がなくても必要です)
- 直近2ヶ月以内の最終残高が確認できるページ
その他の資産をお持ちの場合は高齢福祉課にご相談ください。
※配偶者が町外にいる方は非課税証明書の提出を求める場合がございます。
● 申請する人の運転免許証などの本人確認書類
● 対象者本人の介護保険証・介護保険負担割合証(更新の人は介護保険負担限度額認定証)等の本人確認書類
申請日を含む月の初日から軽減が開始されます。
提出書類がすべて揃った日に申請を受理するため、提出書類に不備があると軽減開始時期が遅れてしまう場合がありますので、ご注意ください。
申請に必要な添付書類は、申請される人がご自身でコピーをご用意ください。
(役場では原則コピーをしません。また、役場にはお客様用のコピー機はありませんので、あらかじめコピーをご用意ください。)
申請書
介護保険負担限度額認定申請書・同意書
介護保険負担限度額認定申請事前チェックリスト・提出前申請書チェックリスト
申請書記入例
郵送での申請受付について
郵送での申請も可能です。
申請書(必ず連絡がとれる電話番号を記載)、同意書、預貯金等の写し、対象者及び申請者の本人確認書類の写しを同封してください。提出書類に不備がある場合、追加郵送いただくことになりますのでご注意ください。
本人確認書類の原本は同封しないでください。
利用者負担段階第4段階の方に対する特例減額措置
住民税課税世帯の方や世帯を別にしている配偶者が住民税課税者である場合は、居住費(滞在費)や食費の負担が軽減されません。
しかし、高齢夫婦世帯等で夫婦どちらかの方が施設に入所して食費・居住費を負担する等により、在宅で生活している配偶者が生活困難に陥るといった事態にならないよう、特定の条件を満たす場合、食費・居住費が軽減される制度(特例減額措置)があります。認定を受けると、所得等の状況に応じて、食費・居住費のいずれかまたは両方において負担限度額の第3段階(2)が適用されます。
特例減額措置の対象者の要件は以下の(1)~(7)を全て満たす方です。
特例減額措置を受けるためには手続きが必要となりますので、高齢福祉課介護保険係までご相談ください。
(1)特定入所者介護サービス費の利用者負担段階が第1段階から第3段階(2)に該当しない、2人以上の世帯の方
(2)全ての世帯員及び配偶者の公的年金等の収入金額+年金以外の合計所得金額から、施設の利用者負担(介護サービスの利用者負担、食費・部屋代)の見込額を除いた額が80.9円以下であること
(4)全ての世帯員及び配偶者について、現金、預貯金等の額が合計450万円以下であること(預貯金のほか、有価証券、債権等も含む)
(5)全ての世帯員及び配偶者について、居住に供する家屋、その他日常生活のために必要な資産以外に活用できる資産がないこと
(6)全ての世帯員及び配偶者について、介護保険料を滞納していないこと
※通常の負担限度額認定とは異なり、施設入所の場合のみ適用となりますので、ショートステイの場合は特例減額措置の対象とはなりません。