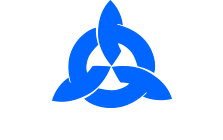各種手続き
- [初版公開日:2023年04月06日]
- [更新日:2023年4月6日]
- ID:1184
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
農地の転用
農地の転用とは、農地等を農地以外のものに用途を変更することを言い、転用を行う場合は許可または届出が必要になります。
※「農地等」とは、地目が農地以外であっても、土地の現況が耕作・採草・放牧の用に供されている土地を含みます
農地法第4条許可
阿見町農業委員会の許可が必要な手続き
市街化調整区域内に存する自ら所有する農地を転用する場合に必要になります。
農地法第5条許可
阿見町農業委員会の許可が必要な手続き
市街化調整区域内に存する農地について、転用目的での売買や貸し借りを行う場合に必要になります。
農地法第4条届出
阿見町農業委員会へ届出が必要な手続き
市街化区域内に存する自ら所有する農地を転用する場合に必要になります。
農地法第5条届出
阿見町農業委員会へ届出が必要な手続き
市街化区域内に存する農地について、転用目的での売買や貸し借りを行う場合に必要になります。
制限除外の農地移動届出
阿見町農業委員会へ届出が必要な手続き
農地の転用には一部許可手続きが不要となるものがあり、それらの転用行為を行う際は、許可申請に代わり制限除外の農地の移動届の提出が必要になります。
なお、電気事業者または電気通信事業者が行う転用行為については、届出書の提出前に事業計画書に基づく調整が必要になります。
農地の権利移動
農地の売買や貸し借りを行う場合は、農地法第3条の許可または利用権の設定が必要になります。
農地法第3条許可
阿見町農業委員会の許可が必要な手続き
農地法第3条の3第1項届出
阿見町農業委員会へ届出が必要な手続き
農地を相続等で取得した場合に必要になります。
利用権の設定
阿見町農業委員会の承認が必要な手続き
農地等の貸し借りを行う場合に必要になります。期間満了により自動的に貸借関係が終了し、離作料等の問題も発生しません。
なお、利用権の設定を行う場合は、農地法第3条の許可は不要になります。
農地法第18条
阿見町農業委員会の許可等が必要な手続き
農地法第3条に基づく賃貸借の解除・解約の申し入れ・合意による解約、または賃貸借の更新をしない場合は、農地法第18条に基づく許可が必要になります。
ただし、合意による解約のうち、その解約によって農地等を引き渡すこととなる期限前6か月以内に成立した合意であり、かつその旨が書面において明らかであるものなどについては、農地法第18条第6項に基づく通知書を提出することにより、許可は不要になります。
また、使用貸借の解除・解約については農地法第18条の許可および通知書の提出は不要になりますが、使用貸借による解約書の提出が必要になります。
農地改良制度
農地改良
阿見町農業委員会の承認が必要な手続き
農地の効率的な利用を図るため、畑のくぼみや湿田の解消また田を畑に転換するなどのため農地に盛土を行う場合は、農地改良になります。
農地改良行為を行う場合は、農業委員会と協議が必要です。
農地改良行為の主な要件は、次によります。
- 土地所有者または小作農者自らが行うもの
- 盛土材は、従前の作土と同等以上であること
- 施工は耕作に支障のない時期で、期間はおおむね6か月以内であること
- 農地面積が3,000平方メートル未満であること
- 盛土による隣接地との段差は、50cm以下であること
- 取得する搬入土砂の所有者または建設工事元請業者の土砂搬出同意書を添付すること
- 隣地所有者の承諾書を添付すること
各種証明
耕作証明
軽油引取税の免税申請や、他市町村の農地を取得する場合などで必要になる場合があります。
農家基本台帳に基づきその世帯または法人が耕作している農地面積を証明します。
農業を営む者の証明
買受け適格証明
農地などを競売・公売等で取得しようとする際の入札参加資格として必要になります。