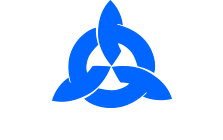児童扶養手当
- [初版公開日:2023年11月07日]
- [更新日:2025年4月24日]
- ID:1087
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
児童扶養手当とは?
父母の離婚などにより、父または母と生計をともにしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進を目的として支給される手当です。
手当の額は?
| 全部支給 | 一部支給 | |
|---|---|---|
| 基本分(1子分) | 46,690円 | 46,680円~11,010円 |
| 2子以降加算分 | 11,030円 | 11,020円~5,520円 |
・児童扶養手当の手当額は、就労等による収入額等に応じて変わります。
児童扶養手当の支給日
支給日は1月(11、12月分)・3月(1、2月分)・5月(3、4月分)・7月(5、6月分)・9月(7、8月分)・11月(9、10月分)の11日で、支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は繰り上げて支給されます。
手当を受けることができる人
次のいずれかに該当する児童(18歳の年度末まで。ただし心身におおむね中度以上の障害がある場合は20歳未満まで)を監護している母、児童を監護し、かつ、生計を同じくする父、または父母にかわってその児童を養育している人が手当を受けることができます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害のある児童
- 父または母が生死不明な児童
- 父または母が1年以上遺棄している児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 母が児童を懐胎したときの事情が不明である児童
手当が支給されない場合
次のような場合には、手当を受ける資格がありません。
児童が
- 日本国内に住所を有しないとき。
- 児童福祉法上の里親に委託されているとき。
- 父または母と生計を同じくしているとき(父または母が一定の障害の状態にある場合を除く)。
- 母または父の配偶者に養育されているとき(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)。
- 児童福祉施設に入所しているなど、受給資格者が養育していると認められないとき(通園は除く)。
父、母または養育者が
- 日本国内に住所を有しないとき
手当を受けるには?
こども未来課に「認定請求書」と必要書類を添えて提出します。
この請求書が茨城県県南県民センターを経由し茨城県知事の認定を受けることで、手当を受けられるようになります。
また、この手当は、受給資格があっても、請求しない限り支給されませんので、注意してください。
所得の制限
受給資格者、その配偶者または同居(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の扶養義務者(父母、祖父母、子、兄弟など)の前年の所得がそれぞれ下表の額以上であるときは、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部の支給が制限されます。
| 扶養親族数 | 全部支給 | 一部支給 | 扶養義務者・配偶者 孤児等の養育者 |
|---|---|---|---|
0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得額の計算方法(課税台帳に基づき計算)
所得額=年間収入額-必要経費(※1)+養育費の8割相当額-下記の諸控除-8万円(※2)
※1 給与所得控除額 ※2 社会保険料等相当額
〇諸控除の額
- 寡婦控除 270,000円 ※受給資格者が母(父)の場合は、寡婦控除・ひとり親控除については控除しない。
- ひとり親控除 350,000円
- 障害者控除、勤労学生控除 270,000円
- 特別障害者控除 400,000円
- 配偶者特別控除、医療費控除等 地方税法で控除された額
所得制限限度額に加算されるもの
(1)受給資格者本人
- 老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合・・・10万円/人
- 16歳以上19歳未満の扶養親族、特定扶養親族がある場合・・・15万円/人
(2)扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者
- 老人扶養親族がある場合・・・6万円/人(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は1人を除く)
現況届
児童扶養手当を受給している人は、毎年8月に前年の所得と養育関係を確認する「児童扶養手当現況届」を、こども未来課に提出することになっています。受給資格者には必要書類を送付します。
この届を提出しないと11月以降の手当が受けられなくなります。また、2年間この届を出さないと資格を失いますので、ご注意ください。
一部支給停止適用除外事由届出書
児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件に該当する人は、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」を、こども未来課に提出することになっています。対象者には現況届の書類と一緒に送付します。
この届を提出しないと児童扶養手当の2分の1が支給停止となる可能性があります。
認定後の届出義務
認定を受けた人は、次のような場合に届出の義務がありますので、事由が生じたときは、すみやかにこども未来課まで届け出てください。
- 対象児童が増えた時、対象児童が減ったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなど現在の支給区分が変更となるとき
- 受給資格を喪失したとき
- 受給者が死亡したとき
- 年金(国民年金、厚生年金など)を受けることができるようになったとき
- 児童が父または母が受ける公的年金の加算対象となったとき
- 受給している年金の給付額が変更になったとき
- 氏名、住所、支払金融機関が変更になったとき
受給資格の喪失
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますので、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を受けた場合、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
- 婚姻の届出をしたとき。
- 婚姻の届出をしていなくても、事実上の婚姻関係(生計を同じくする異性と同居または、同居がなくとも、頻繁な訪問があり、かつ生活費の援助がある場合)になったとき。
- 児童が死亡したとき(受給者本人が死亡したとき)。
- 児童が、児童福祉施設に入所したり、転出などにより、監護または養育しなくなったとき。
- 遺棄、拘禁などの理由で家庭を離れていた児童の父または母が帰宅したとき(遺棄のときは安否を気遣う電話、手紙など連絡があった場合を含む)。
- その他支給要件に該当しなくなったとき。
公的年金給付等との併給
児童扶養手当の受給資格者や対象児童が公的年金給付等を受給できる場合及び対象児童が公的年金給付等の加算対象となっている場合は、その受給額及び加算額の月額が児童扶養手当月額(所得制限後の額)より低い場合にその差額が支給されます。(受給できる場合には、現在受給していなくても申請すれば受給できる場合も含みます。)