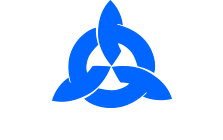阿見町名所百選 阿見小学校地区(その1)
- [2015年1月7日]
- ID:817
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
阿見小学校地区(その1)
町役場をはじめ、中央公民館、図書館、大学病院、国・県立大学など公共施設の集中するこの地域は、阿見町の中心部です。
国道125号バイパス付近にはショッピングセンターなどの商業施設も多く、活気あふれる郊外型商業地域でもあります。
そんな中にもひっそりと歴史は息づき、昔の人の功績をたたえる碑や胸像が地域住民の手によって守られています。
普段は見過ごしているかもしれないそんな小さな名所を、もう一度訪ねてみませんか。
阿見小学校地区 名所百選(その1)
47 湯原一胸像 48 まい・あみ通り(茨大通り) 49 金毘羅神社と鈴木村開拓碑
※各項目に貼られている地図は、名所百選の看板の位置またはその付近を示しています。
※名所百選はわかりにくいところにあるものがあります。詳しくは生涯学習課へおたずねください。
47 湯原一胸像
阿見小学校
【中央南/名所百選No.36】
この胸像は阿見小学校校庭の東南隅に建っています。
湯原一(はじめ)は、旧阿見村若栗の旧家に慶應元年(1865)に生まれ、上京して二松学舎で三島中洲(みしまちゅうしゅう)(漢学の大家のち東京帝大教授)に学びました。
帰郷後、明治20年(1887)に父秀三郎が県会議員在職中に急死したので、若年で家を継ぎ、同25年村会議員、同29年稲敷郡会議員となり、早くから地方政治に関与していきました。
明治36年(1903)には阿見村長となり、以後昭和4年(1929)まで7期にわたり村長を務めました。
湯原一が村政に関与した明治~昭和初期の37年間は、阿見原を中心とした開拓の進展から、一転して海軍飛行場の開設へと、人口の増加と難問の続出を抱えた困難な時代でした。
彼はまず、近代農村の建設のための組織づくりとして、明治34年(1901)に阿見村農会を設立し、同39年には阿見村産業組合を設立、同44年に地主会を設立しました。
また、移住者増加などによる村内不統一や各種の理由で小学校の統合が困難であったものを、湯原は自己所有地を提供することで村民を説得し、明治43年(1910)現在地に阿見小学校が建設されました。
国が指導する地方改良運動の一環として村是の策定にも努め、明治44年(1911)県是実行模範村の指定を受け、さらに納税の向上を図り、大正3年(1914)東京税務監督局長の表彰を受けました。
以上の事績により、自治功労者として藍綬褒章を授けられました。昭和8年没、69歳でした。
なお、小学校の校門はかつての霞ヶ浦航空隊正門を移築したものです。
また、校庭にあるイチョウの木は、小学校開校記念に三区の青年団が寄付したもので、今では町一番の太さを誇っています。
48 まい・あみ通り(茨大通り)
茨大通り
【中郷西/名所百選No.47】
茨城大学農学部の敷地を南北に通る道路は、阿見町を象徴する平和のモニュメントが建ち、街路樹の桜並木の春の風情は、「住んでよかった町」にふさわしいメインストリートです。
通りは県道竜ヶ崎阿見線の中の新町中郷線で、阿見坂下から中郷歩道橋までの距離は1 .511メートルあります。
大正11年(1922)、現在の茨城大学農学部一帯に霞ヶ浦海軍航空隊が開設されました。
現在も往時をしのぶものがいくつか残っています。
中郷保育所の脇に全国の海軍航空殉職慰霊塔があり、台座石の下には、海軍航空殉職者の霊を奉斎した霞ヶ浦神社の御神体であった殉職者名簿がおさめられています。
ながく地域の人たちによって守られてきましたが、平成18年に町へ移管されました。
「まい・あみ・まつり」の会場が移転したことに伴い、現在は茨城県立医療大学前の通りを、「まい・あみ通り」とよんでいます。
49 金毘羅神社と鈴木村開基碑
金毘羅神社
鈴木村開基碑
【鈴木/名所百選No.27】
当社本尊は、寛政9年(1797)2月、四国讃岐の金毘羅宮から、若栗村住人栗山又兵衛他3人が勧請して来たものです。
金毘羅参りはこの時期とても盛んでしたが、約1年有余をかけての長旅でした。
御神体は石板で、これをかついでの旅はさぞかし大変な事であったと思われます。
御神体は野外に置いて祀りました。
明治12年(1979)から始まった鈴木安武の鳳凰原(ほうおうはら)開拓にともない、桂川の水利が大変問題となりました。
すなわち、この桂川にもうけた「どうめき池」を安武が手に入れたので、この金毘羅様と引きかえに鈴木家が当初氏神として祀ることになったといわれています。
その後、鈴木家の衰退に伴って、村の守り神となりました。
鳥居にかかるわらで作った蛇は、開拓により追立てられた蛇をあらわしています。
開基碑は明治32年(1899)6月8日に没した鈴木安武の偉業を碑文にして、没後に建立されたものです。
男爵本田親雄氏が文章を作り、書は織田完之氏に依頼しました。
いずれも安武の友人たちであり、安武の出生から経歴、開拓の心魂と労苦を語り、また鈴木村創立の由来を後世に伝える内容になっています。
台座は御影石、碑石は仙台石で、東京の石屋「井亀」が篆刻し、東京から荒川沖駅まで貨車で運び、駅からは馬車で運びましたが、ぬかるみがひどく、農民が毎日手弁当でかけつけて約7日かかって現在地に到着させたといいます。
明治期の開拓史を語る貴重な碑文です。