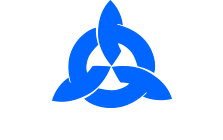阿見町名所百選 君原小学校地区(その2)
- [2019年12月16日]
- ID:810
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
君原小学校地区(その2)
ゆるやかな起伏の多いこの地域には、豊かな自然がそのまま残されています。
君原公民館近くの清明川沿いの田んぼでは、夏になれば蛍にも出会えます。
阿見町特産の県銘柄産地指定・実生スイカが盛んに作られている地域でもあり、大きなビニールハウスがあちこちに見られます。
付近の名所旧跡には興味深い伝説の残っているところも多く、そんな伝説を訪ねて回るのも故郷再発見の醍醐味の一つです。
君原小学校地区 名所百選(その2)
23 塙城跡 24 蔵福寺 25 琵琶堤と合戦場
※各項目に貼られている地図は、名所百選の看板の位置またはその付近を示しています。
※名所百選はわかりにくいところにあるものがあります。詳しくは生涯学習課へおたずねください。
23 塙城跡
君原公民館にある石棺石
【塙/名所百選No.19】
当城跡は塙の小字たてを中心として、海抜30メートル近い台地の突端部に築かれた城で、遺構が良い形でのこっています。
特に「たて」の地には本郭、二の郭があり、土塁、空堀、帯郭(おびぐるわ)、墨櫓跡(すみやぐらあと)などが見られます。
この北側には、低地をはさんで丘陵があり、この丘陵の北側は三重構造の空堀と土塁があります。
このことから、低地は家臣団の居住区と判断され、また地形から水の手とも考えられます。
「たて」の地名からみて、本郭、二の郭の地は古い時代に館として築かれ、戦国後期の土岐氏の時代に、堅固な戦国様式の城郭に改造されたと考えられます。本郭北方の三重の堀も新しい構築だと思われます。
土岐氏による改造の時期は、永禄5年に木原に近藤氏が入った後で現在の阿見町域が土岐領に帰した頃、すなわち永禄前期と考えられます。本城の城主は明らかではありませんが、たて(舘)時代の城主は舘野氏の伝承もあります。
土岐領の頃は、土岐家臣が城番、もしくは城代として駐在したか、土岐の一族の誰かが城主となった(慶弔16年の湯原家文書による土岐五郎のような存在)かもしれませんが、文献不足のためわかっていません。
城跡の西南で君原公民館の構内に、大塚古墳の石室の一部が展示されています。
縦3メートル50センチ、横2メートル40センチ、厚さ45センチの巨石で、旧清明川の橋として架けられた後、堰(せき)の下石として利用されましたが、現在は元の場所におかれています。
塙城図

- PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。
24 蔵福寺
蔵福寺
木造阿弥陀如来立像・脇侍
【追原/名所百選No.2】追原633
追原にある竹生山(ちくぶざん)蔵福寺は、真言宗豊山派の寺院です。
鎌倉時代の宝知2年(1248)、塩断(えんだん)上人が真言律宗として開山しましたが、室町時代に精満上人によって真言宗に改宗したと伝えられています。
初めは塙の東観山にあったようですが、のちに蔵福寺の末寺安養寺があった現在の場所に移りました。
幕藩体制下、阿見町域は21の村にわかれていましたが、そのうち追原をはじめとする12の村が仙台藩領でした。
江戸時代の寛永2年(1625)仙台藩龍ヶ崎領を検分するためにこの地を訪れた伊達正宗が、徳川秀忠より拝領した鷹で鷹狩(たかがり)を行った様子を記した手紙が残されています。
万治3年(1660)には、蔵福寺は伊達家より松を拝領して客殿を建立、安永3年(1774)にも松20本を拝領して増築したと記録されています。
本尊の木造阿弥陀如来座像(あみだにょらいざぞう)は、平安時代後期、安阿弥の作で、町の文化財に指定されています。
また、木造阿弥陀如来立像(あみだにょらいりゅうぞう)と両脇侍は、慶派の仏師有慶による鎌倉時代の作で、時の常陸国守護職小田知重(おだともしげ)の菩提を弔うために藤原時朝(ふじわらのときとも)が建立したものと伝えられ、県指定の文化財になっています。
25 琵琶堤と合戦場
【石川/名所百選No.26】
清明川下流の右岸一帯は、町域の石川地区と美浦村舟子地区が接するところで、広大な水田地帯です。
ここを通るあぜ道は琵琶堤(びわづつみ)と呼ばれており、琵琶法師と、戦国期の合戦に関する二つの伝説が残されています。
「昔このあたりはたいへんな悪路で、村人は通行に困っていました。それ見かねた琵琶法師が命より大切な琵琶を人柱代わりにし、修理工事を完成させたといいます。」
このあたりは清明川の下流にあたり、数本に分かれて乱流して水量も多かったと推測されます。
(近世前期の清明川中流の古絵図から推定)。
水田はまだ無く、一面の湿原であったのでしょう。
村人が排水しながら一本の堤を兼ねた道路を構築する工事は困難な事業で、旅の琵琶法師(ある神格)の神秘的な力を要したという伝説が生まれたと思われます。
初めは法師が人柱になった、それは実は神であった、という構成から変化したのかもしれません。
もう一つの合戦伝説は、「合戦場」や、合戦後に点呼した地を「勘定地面(かんじょうじめん)」、戦死者が田んぼに倒れ込んだ地を「死込(しこみ)」など、従来からの地名を読みかえて合戦の存在を裏付けようとしています。
昔このあたりはさびしい場所であり、美浦村舟子の狐「塚原おせん」と、地元の狐「二の宮ピン助」が逢いびきをしていたところとも伝えられます。