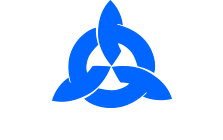阿見の昔ばなし その8
- [2015年3月26日]
- ID:784
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
阿見の昔ばなし その8
22 中嶋なをの墓 23 下吉原の大日碑 24 立の越の大権現様
22 中嶋なをの墓
阿見村(現在の阿見町)の上空に飛行機が飛ぶようになったのは、大正9年からのことです。
当時は操縦技術も研究途上であり、飛行機そのものにも同じような問題がありました。
飛行機は落ちないのが不思議なくらいの考えがありましたし、また、この周辺にはよく墜落しました。
しかし、村民を巻き込んだ事故は、それまではなかったのです。
大正14年6月29日、当日は朝から天気もよく、三区で農業をしている、中嶋家の四女、なをさんは畑の草取りをしていました。
昼近くなって、突然、家の北側の竹やぶの方向からものすごい音が響いてきました。
飛行機が、草取りをしていたなをさんの近くに墜落したのです。
その瞬間、なをさんは、翼の部分で腕をもぎとられ、出血がひどく海軍医務室で息を引き取ってしまいました。
なをさんは当時16歳でしたが、「結婚するなら飛行士へ」と若い心を燃やしていたというのです。
墜落した飛行士は、名古屋出身の海軍将校で独身でした。
なにかの縁かと、名ばかりの結婚式をあげさせて、野辺の送りをすませたという話です。
三区の道路の片隅に、今もひっそりとその墓は立っています。
※中嶋なをさんのお墓は、道路整備により、現在は別な場所に移動しています。

23 下吉原の大日碑
下吉原に大日というところがあります。
桂川に沿って田んぼが広がり、岸に沿って深い森があります。
この森の中に、昔、村人たちが、五穀豊穣と家内安全を祈って建てた大日碑が、こんもりとした塚の上にひっそりと建っています。
昔は、年に一度お祭りをし、お祈りをしていたおかげか、稲穂もよく実り、畑でもきゅうりや大根がたくさんとれて、村の暮らしも豊かになっていったということです。
さて、この川に棲んでいたのんびり屋の河童の三平は、牛久沼の花子に夢中になっていました。
このお祭りを見ていた三平は、ある夜、この碑をきゅうり好きの花子へ手土産にして、沼のほとりできゅうりを実らせてやろうと思い立ちました。
やぶ蚊に刺されながら、塚の上の碑をウンウンいいながら背負うとしてみましたが、びくともしません。
それでもあきらめず、夜明け近くまでがんばってみましたが、背負えません。
そのうちに、背中の甲羅がブツッとつぶれてしまいました。背中がポコポコになり、やっとあきらめました。
大日如来さまの罰を受けてしまったのです。
その時、大日山に日がさしてきました。
三平は、痛い思いをして川にすごすご帰って行きましたが、今でもその碑に甲羅をこすった跡が白く残っているということです。
大日碑(だいにちひ):江戸時代の初めに大日如来の信仰がさかんになり、土を盛り上げて、その上に碑をたてた。
五穀豊穣(ごこくほうじょう):米・麦・あわ・きび・豆などが豊かに実ること。

24 立の越の大権現様
現在は、静かな住宅地となっている立の越の権現山に、今から百年ぐらい前まで、熊野大権現(だいごんげん)様を祀った社(やしろ)が建っていました。
今から850年ほど前の日本では、地震などの天災地変がとても多く、村人たちはたいそう苦しんでいました。
そこで、くらしの平穏無事を願った人々は、あちらこちらに一斉に社を建てて、神様を祀りました。
歳月は過ぎて、立の越にも権現様が祀られました。
権現様に対する人々の信仰心は厚く、八里四方の村々から大勢の人たちがお参りに来るほどでした。
お参りする人々の行列は、社を中心にして「の」の字のように連なるほど多かったので、「ののびきにお参りの人が来た。」と言われていたそうです。
境内の入り口にあった椎の木は、子ども10人ぐらいで取り囲むほどの神木であり、内側は大きなうろになっていて、その中で子どもたちは遊んだそうです。
その後、権現様は神主がいなくなったので、社に納められていた品々は、中郷の阿弥神社に移され、社は取り払われてしまいました。
今は神社の鳥居の礎石が二個、阿弥神社の林の中に残っています。
また、取り払われた跡に小学校の前身校が建てられましたが、この小学校も別の所に新しく建て替えられました。