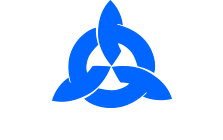阿見の昔ばなし その3
- [2016年12月18日]
- ID:777
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
阿見の昔ばなし その3
7 姫塚 8 どうめき橋 9 新町ものがたり
7 姫塚
飯倉の鹿島神社から若栗に通じる道路を約二百メートルぐらい行くと、右側に土饅頭(どまんじゅう)の小さな墓がありました。
この墓を村人は姫塚(ひめづか)と呼んでいました。まことに粗末な墓で、もとはうっそうと繁った松の大木が生えていました。
この墓の主は、江戸崎城主土岐(とき)氏の姫であると言い伝えられています。
墓を何百年も守り続けてきたのは、当時の名主であった石引家です。
飯倉は当時、土岐氏の支配下にあり、城を守るのに重要な所でした。
この墓の五十メートル先には大木戸があり、守備の武士がいたようです。
大木戸の両側は堀で、更に六百メートルぐらい行くと二重堀になっていて、今でもその名残りが見られます。
天正18(1590)年、豊臣秀吉が小田原の北条氏を下すと、味方同士であった江戸崎城も佐竹義宣(よしのぶ)の軍に攻められ、あえなく落城してしまいました。
城主治綱(はるつな)は上之島(現在の稲敷市)に逃れて、多くの武士たちはあちらこちらに散ってしまいました。
その時、まだ一歳半のあどけない姫も、乳母(めのと)に連れられて家臣の石引家に身を寄せました。
山深い飯倉の地を選んだのは、豊臣軍から見つけられないためだろうと言われています。
その頃疫病がはやり、姫もそれにおかされて、まもなく亡くなったそうです。
落城の悲運と病におかされた姫の運命は、まことに哀れでした。これも宿命と言うものなのでしょうか。
ところで、村にはもう一つの言い伝えがあります。
姫は幼児ではなく17歳ぐらいの面長の美人でした。
髪の毛は長く漆黒で、目は水晶のように澄んで輝き、微笑を絶やさぬ方であったとも言われています。
落城後、石引家に身を寄せたということです。朝に夕に、江戸崎の方を眺めている姿は、誠に可憐であったと伝えられています。
落城前に将来を誓いあった美少年の武士がいて、どこへ逃れていったのか、もしや敵に殺されはしまいかと、日夜恋いこがれ悲しむ姿は、まわりの人々の涙を誘うほどでした。
やがて、姫はあまりの悲しさにだんだん弱り果てて、この山里で亡くなったとも言われています。
いずれにしても、飯倉に逃れて来た悲運の姫は、石引家の手厚い供養と村人の温かい心に包まれ、この地でおだやかに眠っていることでしょう。
現在は開発により、姫塚も昔の位置より移動され、道路の脇にひっそりと残されています。
※姫塚はその後、工業団地の開発造成に伴い道路の反対側にうつされました。土饅頭はなくなりましたが、石引家が供養塔を立て、現在も管理、供養を続けています。

8 どうめき橋
若栗と鈴木の境を流れる小川を桂川といいます。
昔、ここに「どうめき橋」という小さな丸木橋がかかっていました。
この地には豪族の館があり、橋の下の川は堀にもなっていたそうです。
戦乱が続いていた頃、小豪族の運命ははかないものでした。
「今日は東、明日は西」「昨日の味方は今日の敵」という具合に、勢力の強い主をたよって、右に左に揺れ動いていました。
取入れもすんだある年の暮れ、一族を率いて遠い戦場へ出陣して行った豪族は、冬が過ぎ春が来ても、とうとうこの地に帰って来ませんでした。
館に残された家族の悲しみは深く、ことのほか姫の泣く声は、朝に夕に、さざ波が寄せるかのように里人の耳に聞こえ、耐えがたい悲しみを誘いました。
その姫もいつしかこの館から消え、館とおぼしき跡とさらさらと流れる水堀だけが残されました。
その後、夜にこの橋を渡ると、桂川の流れの中からしくしくと姫の泣き声が聞こえるというので、夜は里人の往来もとだえたそうです。
桂川も蛙がはねる水音が最近まで聞こえていましたが、今は川の改修が進んで、昔の面影をわずかにとどめるに過ぎなくなっています。

9 新町ものがたり
1.新町の誕生
大正十一年、阿見村青宿に霞ケ浦海軍航空隊の水上班ができました。
それがだんだん大きくなって日本海軍の拠点となり、外国から飛行家のリンドバーグ夫妻が来るほど有名になりました。
そこで、各地から何か仕事をしようと大勢の人たちが移り住んで、水戸屋(水戸)、徳島屋(徳島)、秩父屋(埼玉)、京屋(京都)、備前屋(広島)、伊勢屋(三重)など、自分の故郷の名前をつけて、商売を始めました。
そのうちに風呂屋、映画館、玉突き場、郵便局など次々にでき、「新町には、よそいきの支度で行く。」と言われるほど賑わいました。
こうして、昭和の初めごろ、青宿の地に新しい町ができたということから、「新町」と名づけられました。
2.大日山の神様
「ほら、やっぱり悪いことが続く。山の神様が怒ったんだ。」
新町の高台は、廻戸から青宿の方までつながる山で大日山といいました。
この山には、荒神様という気性の荒い神様がおりました。
海軍航空隊の開設のために、この山を崩して田んぼを埋めたとき、人々は山のたたりを心配しました。
やがて、工夫たちが大けがをしたり、工事の監督が亡くなったりして、たたりの噂はしばらくの間、人々をこわがらせました。
人々はたたりを鎮めるために、大日山の一角におまじないの土器を埋め、その上にお堂を建てました。
今でも小高い丘があり、大日様が祀ってあります。三尺下には、土器が埋まっているかもしれません。
3.チンチン電車が走っていた
一両の電車が土浦、新町間を走っていました。
「常南鉄道」といい、一時間に3、4本で朝5時から夜の12時まで走っていました。
今の多田石油店の裏に車庫や駅があり、「チンチン」とかねを鳴らして出発の合図をしました。
料金は片道7銭でした。このころのおまんじゅうは十銭で七個買うことができました。
海軍の若い兵隊さんたちは足を鍛えるため歩きましたが、海軍関係の多くの人たちが利用していました。
この電車で土浦の学校へ通った人もいました。
そのうち大正15年に走り始めた電車は、いろいろな事情で昭和13年に閉鎖されました。
最後の日にはきれいに飾った花電車が走り、子供たちは後を追って走りました。
4.サーカスが来た
大日山は、霞ケ浦がよく見渡せる所です。ここの空き地には、よく柿岡サーカスが来て、客寄せの楽隊が町中を練り歩きました。
馬・犬・猿が主な動物で、ライオンなどはいませんでした。
入口の一段高い所にいる人が、「さあ、おもしろいよ。ちょっと見てごらん。」
と呼びかけて、ちょっとだけ入口を開けて中を見せてすぐしめるので、人々はとても見たくなりました。
「ねえ、連れてってよ。連れてってよ。」
子供たちは親にせがんで、ドキドキわくわくしながら見に行きました。
また、動物園を作る計画もあって、切符を売る小屋まで建ちました。
いろいろな事情で動物園はできませんでしたが、切符売り場は夜警小屋として、しばらく小林酒屋さんの前あたりにありました。
「動物園は、とりやめなんだって。」
「なあんだ、つまんないな。」
子供たちは、とてもがっかりしました。
銭(せん):円の下の単位。円の百分の一。
夜警小屋:町内の住民が夜間、火事や盗難を防ぐため、当番にあたる人のために作られた小屋。