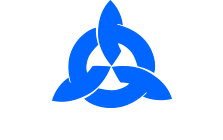阿見の昔ばなし その2
- [2016年12月19日]
- ID:776
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
阿見の昔ばなし その2
4 柿の木橋 5 本郷の大六天 6 お安稲荷
4 柿の木橋
武器学校(陸上自衛隊土浦駐屯地武器学校)の西側、青宿から立の越へ向かう旧県道の精進川(しょうじんがわ)にかかる橋を、柿の木橋と呼んでいます。
橋の名前のいわれには、二つの言い伝えがあります。
一つは、その昔日本武尊(やまとたけるのみこと)がこの地を通りすぎようとした時、大水で渡れないので、近くの柿の木を倒して渡ったという言い伝えです。
武尊は、陸奥の国(今の青森県全部と岩手県の一部)の騒乱を静めるために船で陸奥に向かう途中、暴風にあい、最愛の妻を亡くしました。
船は破損し、たびかさなる強風と高波に襲われつつ、命からがら上総の国(今の千葉県)になんとかたどり着きました。
武尊は、鹿島・香取あたりで兵をまとめ、船や徒歩で進みました。
花室川までやって来ると、洪水で橋が流されていて一軍は渡ることができませんでした。
そこで兵士たちが、川のそばに生えていた柿の大木を切り倒して橋をかけ、無事に渡ることができたことから柿の木橋と呼ぶようになったという話です。
また、次のような話から生まれたという言い伝えもあります。
この里に、姿が特に美しい花子という娘が住んでいました。
年頃になり、作男である次郎吉に恋をし、人目を忍んで逢っていましたが、いつしか親の知るところとなりました。
父母は花子を次郎吉と別れさせ、他の家に嫁がせようとしました。
そのことを二人が知るようになり、悲しみのあまり、父母の目を逃れて駆け落ちをしてしまいました。
その時に、橋の上に書き置きを残していきました。
以来、この橋を「書き置き橋」と呼んでいましたが、いつの頃からか柿の木橋と呼ばれるようになったということです。

5 本郷の大六天
大六天(だいろくてん)とは、仏教ではもろもろの欲望の最高位にある仏で、極めて自由自在勝手気ままな摩天であるとされています。
しかし、神仏習合の我が国では、この外来の仏を子どもを授ける神、あるいは縁結びの神として、
かなり古くから各地でしめ縄を張って祀るようになりました。
さて、阿見町内にある大六天とその地名は、今では上条・若栗・西郷・本郷など数か所です。
これらのうち本郷の大六天のみが、「荒川本郷字大六天」の地名と乙戸川にかかる「大六天橋」の名前を残して、
どこに消えたのか、そのあとすら見当たりませんでした。
大六天を祀ってある多くは古道や鎌倉街道沿いにあり、そのほとんどが戦国時代の城砦集落の中にあります。
本郷の大六天も鎌倉街道(現在の中根~上本郷)に沿って、眼下に乙戸川を望む台上にあったのではないかと考えられていました。
阿見町内の大六天は、社殿のあるものや石の祠だけのものもあり、いずれも何百年にわたり、人々の願いをこめて
それぞれの時代を生き抜いてきたものです。
特に、江戸時代から明治にかけて栄え、江戸幕府の貞享二(1685)年阿見野野論裁許状村絵図(あみのやろんさいきょじょうむらえず)にも
描かれている西郷の大六天は、今は小さな祠のみとなりましたが、最近真新しい鳥居も建てられ、よく手入れされています。
古い地名まで残している本郷の大六天は、その後下本郷の下村さん宅の氏神として同じ場所に代々祀られていることがわかりました。
その場所は、乙戸川を見下ろす高台にあり、何百年も経た今は、宅地に変わりわからなかったのです。
下村さん(村の古老)の話によれば、祖父の代にこの土地を求めた時、地主さんから「この神様は大切なもので、大事にして欲しい。」と
言い残されたそうです。
また、昔はここに古いお寺があったとみえ、宅地造成の時にそれらしい礎石の一部が出土したということです。
摩天(まてん) 人をまどわす仏のこと。
神仏習合(しんぶつしゅうごう) 神道と仏教を組み合わせた考え方。
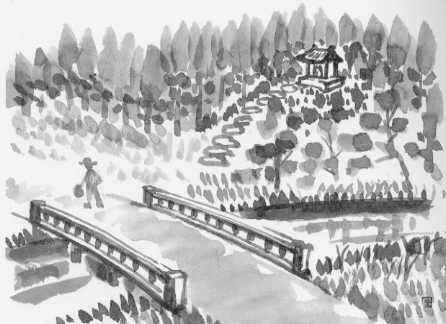
6 お安稲荷
乙戸川上流の上小池地区に、お安稲荷という小さなお宮があります。
もともとは、今から四百五十年程前の戦国時代に、吉田家の下屋敷に祀られていたものです。
なにしろ永い歳月を経ているため社(やしろ)は朽ち果て、御神体の石のみがただ一つ、森の中にひっそりと残されています。
ある日のこと。この近くの若者が薪を取りにこの森に入ったところ、急にあたりがパッと輝き、目の中に光がとびこんできました。
「ワッ! これはなんだ。」
驚いた若者は急いで家に戻りましたが、三日三晩うわごとを発して寝込んでしまいました。
心配した家族が駆けつけ、若者の言う事を聞いてみると、「筆と墨を…。」
と言うので、すぐに持ってくると、「石の宮、九尺二間の宮つくれ」と書き記しました。
家の者はさっそく地主にことのいきさつを話し、親戚や村中から浄財を集め、言われたとおりのお宮をつくったところ、若者は嘘のように元気になりました。
稲荷のお宮が完成してまもなく、鉾田の駅前にあるそば屋の主人が、「お安という白狐のお告げをうけた。」と言って、はるばるお宮を訪れました。
そこで、この稲荷をお安稲荷と名付けるようになったといいます。
時は移り、戦火は中国大陸から南方諸島へと拡大しつづけました。
このお稲荷さんに祈願した若者達は不思議にも元気で帰ってこられたので、このうわさが広がり、遠くは谷田部、小野川あたりからも多くの出征兵士が続々と訪れるようになりました。
ある年の暮れ、巫女としてこのお稲荷さんにつかえていた地主の妻は、病に侵され医者からも見放されていました。
ある日、地主は土間の方で、何か白いかげがフッと飛び降りるような気配を感じました。
この事があってから、妻は日ましによくなり、三年ほど長生きをしたといいます。
今も上小池の森の中に白狐は生き続け、人々の安らかな暮らしを見守っているということです。
浄財(じょうざい):神社に寄付するお金のこと
出征(しゅっせい):戦争に行くこと